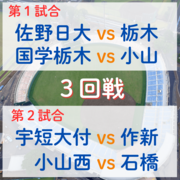原発の高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分事業を担う原子力発電環境整備機構(NUMO)は23日、地層処分技術や国内外の動向を紹介するシンポジウムを札幌市で開いた。理解醸成が狙いで約100人が参加。専門家らが講演し、候補地を選ぶ際の地質条件や調査手法などを紹介した。
国際原子力機関(IAEA)で放射性廃棄物処分部門のチームリーダーを務めるステファン・マイヤー氏は昨年、試験操業を始めたフィンランドの最終処分場「オンカロ」など海外の動向を説明。候補地を選ぶには地質調査に加えて「地域住民との対話が重要だ」と述べた。機構の柴田雅博理事は「選定に必要となる地質構造の解析は向上し、技術的な準備は整っている」と強調した。
機構は、2020年から最終処分場選定の第1段階である「文献調査」を北海道寿都町と神恵内村で実施し、昨年11月に報告書を公表した。寿都町全域と神恵内村の一部を次の段階となる「概要調査」の候補地としたが、鈴木直道知事は反対の姿勢を崩していない。佐賀県玄海町でも昨年6月に文献調査が始まった。
この記事は会員限定記事です
「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする