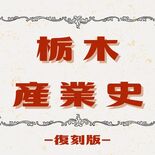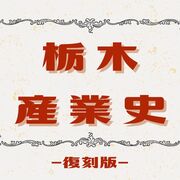20日の東京外国為替市場で、対ドル円相場が32年ぶりに一時1ドル=150円台に下落した。21日も一時1ドル=151円台後半まで一段と円安が進んだ中、歴史的な円安の背景や今後の見通し、栃木県経済への影響などについて、白鴎大経営学部の嶋中雄二(しまなかゆうじ)教授(景気循環論)に聞いた。
-150円台は1990年8月以来、32年ぶりの水準となる。
「円安ドル高は、日本の金融緩和維持も一因だが、ほとんどの原因は米国側にある。オーストラリアドルなど資源国の通貨も売られており、日本円だけではない。結局はドル高だ。11月の中間選挙を控え、米国のバイデン大統領は世論を意識してインフレ対策を優先している。結果として、米連邦準備制度理事会(FRB)による大幅な金融引き締めが正当化されている。なぜインフレ対策にドル高が有効かというと、輸入品の物価を抑える役割があるからだ」
-ドル高が続く。
「マネーストック(金融機関を除いた市場に流通する通貨量)はインフレ率に先行して動く。米国では既に、マネーストックの伸びが大幅に鈍化している。明らかにインフレは転換点を迎えているのに、1ドル=150円台というのは行き過ぎた水準だ」
「なかなかドルが下がらないのは一時的な要因もある。例えば、米国の消費者物価指数が市場予想を上回ったことは一時的なことだったが、『さらに利上げが続くのではないか』という市場心理につながった」
「円安進行は、150円台前半で終わると思っている。米国では、軍需に支えられて景気が堅調で、雇用情勢も良い。中間選挙が終われば、バイデン氏のインフレ対策の主張も下火になるだろうし、世論の関心も薄れる。金融引き締めの効果が表れ始め、徐々に景気悪化を懸念する声も出始めるかもしれない。中間選挙を転換点に、来年3~4月までに、緩やかに140円台前半に向けた動きが出てくるのではないか」
-為替相場の急激な変動に加え、資材高も続く。
残り:約 933文字/全文:1780文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする