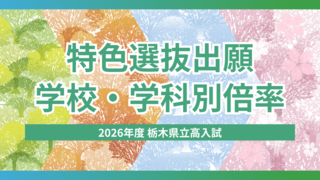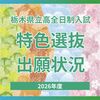来年80回目を迎える県芸術祭を盛り上げようと、県と県文化協会が準備を進めている。出展者数の伸び悩みなど課題はあるが、全国的にも歴史ある事業を県民に再認識してもらう絶好の機会だ。節目を祝うだけでなく、大胆な手法で幅広い世代が魅力を感じられる祭典を期待したい。
県などは記念事業の一環としてポスターのデザインを初めて公募した。交流サイト(SNS)による周知も奏功し応募数は約2カ月で56点。このうち20代以下が5割超、30代以下で約8割を占め、若い世代の関心を集めた。現在、県ホームページで最終候補4点の県民投票を実施しており、イメージを刷新した芸術祭の「顔」が期待できそうだ。
また、芸術文化にかかわる本県ゆかりの個人・団体を網羅した「栃木県芸術名鑑」も18年ぶりに改訂する。かつては3千人以上を記載したが、今や名鑑自体を知らなかったり掲載を遠慮したりするケースもあり、原稿収集に苦労しているという。編集委員らが「本県の芸術文化活動の基礎的資料、県民の情報源となるよう充実させたい」と意気込むだけに、本県文化の軌跡を網羅した一冊にしてほしい。
節目を彩る準備が進む一方、芸術祭の出展者数は芳しくない。今年の79回は個人参加の文芸が過去最少の183人、洋画、彫刻、工芸は横ばいの252人だった。若年層の関心が薄れ出展者が60代以上に偏る中、有効な打開策を打ち出せていないのが現状だ。
こうした中、県が今年実施したメディア芸術に関するアンケートによると、アニメーションやグラフィックデザインなどを手がける若年層の多くが、作品PRの機会や創作活動の充実などを求めている。この機を逃さず、「メディア芸術部門」を芸術祭の一角に加えてもいい。祭典の目玉にもなるだろう。
また入賞作品の展示期間が短く認知されにくい。本県ゆかりのアーティストが発表の場として利用できるアーティストバンクスポットと連携し、身近な場所で良質な作品に触れる機会があってもいい。
芸術文化は県民の関心が薄れれば継承、発展が難しくなる。県立美術館が今秋成功させた企画展「親愛なる友フィンセント 動くゴッホ展」の例もある。次代につながる芸術祭を目指し、県などには既存のイメージにとらわれない提案を望みたい。
 ポストする
ポストする