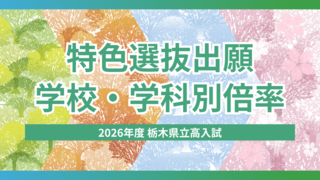「これはすごいね!こんなウイスキー、どんなやつが造っているんだ、みたいな感じで、思いのほか好評価を得ました」。
8月上旬、西堀哲也(にしぼり・てつや)専務(35)が高級日本酒の営業で米国に行った際、ワシントンD.C.でウイスキーを数多く取りそろえている有名なバーに寄り、「哲-TETSU-」の小山エディションと日光エディションを試飲してもらった。すると、店の関係者が集まり、「これで3年の熟成なのか」「こんな面白いフレーバーはどんな樽を使ったら出せるんだ」と次々に質問が飛んで来たという。
スコットランドではウイスキー熟成にはオーク材の樽しか使えない決まりがある。「杉で作った樽の香りをとても新鮮に感じたんでしょうね。ジャパニーズウイスキーらしさを感じてもらい、新しい物好きの国民性からポジティブに受け入れてくれた」と話す。
西堀酒造は2年前から、日本酒を輸出するにしても高級路線に切り替えていた。1本10万円しても購入してくれる富裕層をターゲットにした高級酒を売り込み、販路を開拓している。
西堀酒造で造るウイスキーは、そもそも製造量が少ない。好評で手応えがあったことから来春には米国への輸出、しかもカジュアル層対象ではなく、今回のバーのような富裕層対象にそれなりの価格で輸出に動く予定だ。
日光街道小山蒸溜所は既にさまざまな試飲イベントに出店し、ウイスキーの試作品を試飲提供してファンの声を聞いている。10月5日、ライトキューブ宇都宮全館を使い、95のブースにウイスキー、スピリッツの蒸留所などが集まった「ウツノミヤ・スピリッツ・マルシェ」にも出店した。ファンは開場と同時にお目当てのブースに足を運び、同蒸留所の前にも列ができた。その数も人気の有名蒸留所と遜色はなかった。

清酒酵母や吟醸粉のこと、和樽で熟成させたこと。ファンはそうした情報を頭に入った上で試飲に臨んでいた。埼玉県春日部市から来た会社員(28)は「甘味、吟醸香が感じられ、それは清酒酵母由来なのかと思えた。特にグレーンは他と味わいが異なり、おいしかった」と満足そう。ファーストリリース予定のブレンデッドウイスキー「日光エディション」を予約しているという。西堀専務はこの日、ファンからの期待の声をいただき、「これまで目指してきた方向が間違っていなかったと感じた」と受け止めた。

10月下旬に特約店で引き渡されるバーボン、シェリー、シャンパン、コニャックなどの樽で熟成させたシングルモルト「小山エディション」、吟醸粉を原料にしたグレーン原酒とモルト原酒をブレンドして最後に日光杉の和樽で熟成させた「日光エディション」。9月初め、各千本を瓶詰めした。「しかし、何とも納得いかなかった」と西堀専務。一度詰めた瓶を開け、再度、ブレンドし直し、詰め直したという。各方面からの期待の声が重圧になったことがうかがわれる。

特約店分をすべて出荷した。25、26日の自蔵直売所販売日には開店と同時に購入者がひっきりなしに訪れた。用意した各100本のうち予定数を完売した。小山市内の会社員(53)は「ハイボール好きなので、普段飲んでいるウイスキーとの違いが楽しみ。世話になった人にも贈りたい」と言い、3本購入した。セカンドリリースは来秋になる。

ウイスキーは、発酵、蒸留の製造工程が重要だが、熟成も鍵を握る。さまざまな気候、気象条件、環境により熟成も変わり、酒質、香り、味わいも異なってくる。西堀酒造日光街道小山蒸溜所はこの点にも独自の取り組みを探る。拠点の小山以外に日光市大沢地区、宇都宮市大谷町の大谷石地下採掘場という3カ所を確保した。

小山は寒暖差が激しく、季節の呼吸に合わせて原酒が激しく膨張と収縮を繰り返し、若々しい力と躍動を刻むという。日光は山間の澄んだ空気に抱かれ、四季の穏やかな振幅の中で穏やかな調和と複雑な陰影が育まれる。そして地下60メートルと20メートルの大谷の地下蔵は、温度約10度と湿度90%が年間通して変わらず、静かでひそやかな長い時間が原酒に深遠の熟成を与える。
小山は3年で琥珀(こはく)色に熟成するなど、熟成速度が速い。一方、大谷の地下はスコットランドの気候に似て熟成が遅く、長期熟成に適している。大谷の熟成ウイスキーは最低でも5年以上熟成を行い、2027年以降にリリースする予定だ。

今後、日光でも本格的に貯蔵を行うほか、県内の主なところで貯蔵庫を確保して熟成を構想し、さらには蒸留所整備も描く。例えば、観光地であれば、那須とかで熟成し、那須エディションのご当地ウイスキーを提供し、観光振興につなげる。西堀専務は「これら各地で熟成させた原酒をブレンドすれば、それこそ栃木県ならではのウイスキーになる」と期待する。
西堀専務はブランド解説の冊子で「世界は、差異があるからこそ面白い。本流や起源は、異なるものとの対比によってこそ、一層際立つ。私たちは、世界酒の大舞台に日本の精神を映し出す」と覚悟を示している。栃木県のお酒の歴史に新たな1ページを開いたことに違いない。

 ポストする
ポストする