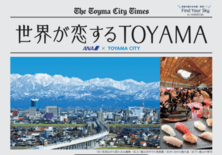阪南大学・末田教授、視覚障がい者向けヨット操船 支援システムでパラスポーツの可能性を拓く
阪南大学(所在地:大阪府松原市、学長:平山 弘)総合情報学部 総合情報学科の末田航教授は、視覚に依存せずにヨットを操船できる「聴覚による感覚代行(感覚の翻訳)技術」を応用した操船支援システムを開発している。
視覚障がい者が自律的にセーリングを楽しむことを可能にするこの研究は、ICTによる“海のバリアフリー化”を通じて、DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)社会の実現を目指す新たな挑戦として注目されている。
背景と研究の着想
セーリングは風や波の変化を「読む」感覚スポーツであり、視覚への依存度が高いことから、これまで視覚障がい者が自立して操船するのは困難とされてきた。末田教授は、障がいのある方が「風を感じて海を走る」体験を安全かつ自律的に楽しめる方法を模索する中で、センサー技術と音声・触覚フィードバックを組み合わせた“視覚に頼らない操船”の可能性に着目。以前から行っていた自動・アシスト帆走の研究を基盤に、「技術が人の感覚を補完し、誰もが海を楽しめる仕組みを」という理念のもとで研究をスタートさせた。
実証成果
2025年6月、小型ヨット自動操舵システム(改良型ハンザ2.3型ディンギー)「RoboHansa」を酒田港から飛島までの33.6kmの航路で渡航することに成功。この航海は、AI操舵がセーラーの意図を予測し、手動操作を補完する「人船一体」に関する研究の一環として行われた。最大風速13m/s、波の高い海況にもかかわらず、RoboHansaは自動で操舵を最適化し、視覚障害者向け音声ナビゲーションがセイル操作をサポート。7時間で航海を終え、平均速度は4.7km/hでした。これは、ハンザ2.3型としては世界初の単独での長距離航海であると考えられている。
【主な成果】
・風向・船体の傾き・進行方向をセンサーで取得し、音や振動に変換して提示
・強風・高波下でも安定した自律操舵を実現
・視覚障害者向け音声ナビゲーションがセイル操作をサポート
今後の展開
2025年11月1日・2日開催予定の「全国ハンザクラスブラインドセーリング大会2025」(場所:伊勢市大湊町 ゴーリキマリンビレッジ・マリーナ伊勢及び宇治山田港)では、感覚代行デバイスである「SoundTellTale」を用いた実践的な操船支援を予定している。今後は、健常者と視覚障がい者が同じフィールドでセーリングを楽しめるインクルーシブな競技環境の整備を目指すほか、教育現場での活用や他のパラスポーツへの展開も視野に研究を進めている。本研究は、「移動の自由」や「スポーツを楽しむ自由」を技術で支えるとともに、教育・福祉・スポーツ分野における包摂的デザイン(Inclusive Design)の新たな可能性を示す取り組みである。
先端技術で『海のバリアフリー』を実現
学校法人阪南大学
10/24 10:00
速報
-
 10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
 10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
 10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
 10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
 10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
 10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
 10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
 10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
 10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署
 ポストする
ポストする