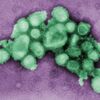崩落した幹線道路の復旧工事や倒壊した数々の家屋、公費解体後の雑草が生い茂った宅地。昨年元日の大地震に続き、昨秋には豪雨被害にも見舞われた石川県能登半島の被災市町を先月末、地元紙などの呼び掛けで取材し、被害の甚大さと復興までの道のりの長さをまざまざと痛感した。
発生から約3カ月間の石川県の初動対応を巡り、外部識者による第三者委員会が今年8月に「能登半島地震対策検証報告書」をまとめた。県の災害対応意識の欠如や広域避難対応の想定不足など問題点や課題を洗い出し、組織体制の見直しや避難所運営の改善策などを明記した。
地震や豪雨の自然災害はいつ、どこで発生してもおかしくない。石川県は報告書の全文をホームページで公開している。被災地の検証結果から得られる教訓を本県や市町も謙虚に受け止め、防災力の一層の向上に役立てたい。
報告書は被災者支援や広域避難など七つのポイントについて提言している。避難所ではライフラインが長期的に途絶することを事前に想定できず、トイレカーや入浴施設の資機材を備蓄していなかった。改善策としてこれらの資機材整備のほか、避難所運営マニュアルの改定を挙げる。
何より災害発生時の県組織の姿勢が問われよう。第三者委は「全庁体制で対応する意識が希薄で対応が受け身。『災害時』の基本的な考え方に課題があった」と指摘する。
さらに県は職員を連絡要員として被災6市町に派遣したが、市町側から「県職員は指示がなければ動かず、何をしているのか分からなかった」と厳しい意見も出た。報告書は危機管理監室から危機管理部への改組・機能強化や、県職員の災害対応力や連携調整能力の向上を求めている。
石川県幹部職員17人のインタビューも掲載している。馳浩(はせひろし)知事は「県庁全体の反省点ですが、災害時に誰がどの役割を担うのか合意事項が共有できていなかった」などと自戒を込めた。結果的に対応が後手後手に回った最大の要因だろう。
能登半島地震の死者は災害関連死を含め600人超に上る。報告書の提言は孤立集落対策や広域避難調整のマニュアル整備など多岐にわたる。本県自治体に限らず、公的機関や民間団体なども被災地の教訓を平時の備えや防災意識の向上に生かす必要がある。
 ポストする
ポストする