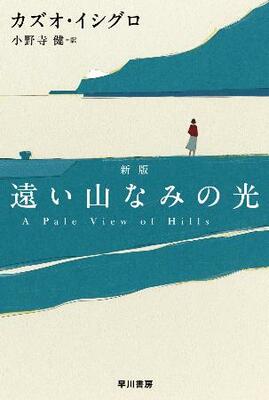長崎市生まれ、英国育ちのノーベル賞作家カズオ・イシグロさんが1982年に発表した最初の長編小説「遠い山なみの光」が石川慶監督によって映画化された。映画は1950年代の長崎の街を主な舞台に、原爆によるトラウマにふたをするように戦後の復興期を生きた人々の姿を描く。イシグロさんにとっては自身のふるさとの物語であり、母親の世代の物語。それを、執筆から30年以上を経て、次の世代が語り直す試みだ。第78回カンヌ国際映画祭が開かれたフランス南部のカンヌで共同通信のインタビューに応じたイシグロさんは、戦争体験者がいなくなる中で、両親から受け継いだ記憶を、さらに若い世代に伝えていく責務があると語った。(聞き手=共同通信 田中寛、橋本亮)
(1)意識した日本映画の伝統
―原作で、戦後間もない困難な時代に、自由であることを求めた女性の姿を描いたことに先見性を感じました。なぜそうしたテーマを書こうとしたのでしょうか。長崎で被爆したイシグロさんの母親の影響はありますか?
「私がこの作品を書いていた1980年当時、私の周りにいた若い女性はみんな、フェミニズムに強い関心を持っていました。後に私の妻となるガールフレンドもそうでしたし、若い男性も同じように関心を持っていました。私たちが年を重ね、互いに関係を深めていく中で、フェミニズムはまさに話題の中心の一つでしたし、それ以上のものだとも思えました。ですから、当時の若者であった私にとって、そうしたテーマで書くというのは極めて自然なことでした」
「付け加えると、最初の長編小説であるこの作品を書く時、私は50年代の日本の映画から多くを学びました。実際、その頃の日本映画には奥深い伝統がありました。当時の映画は通常、男性の監督によって作られますが、日本の作品には女性の地位や立場を扱うものも多くありました。とりわけ成瀬巳喜男、溝口健二の映画は、困難な社会で葛藤する女性の登場人物を中心に据えた素晴らしい作品でしたし、その登場人物を高峰秀子のような素晴らしい俳優が演じました。私はこうした日本映画の伝統を意識していました。私にとって、この時代を舞台に物語を書く時に、こうした観点から考えるのは自然なことでした」
「さらに私が考えていたのは、私の母や母の世代のことです。私の母は30代前半で日本から西洋に移住しました。この二つの社会では女性の地位というものがどれほど違っていたのだろうかと、興味は尽きませんでした」
(2)社会や国は何度でも生まれ変わる
―映画と原作を比較した時に、広瀬すずさん演じる主人公の義理の父親「緒方さん」の描かれ方が印象的でした。映画では、古い世代である緒方さんが「オムレツくらい、一人で作れるようにならんといけんな」と語るシーンがあります。この場面は、原作よりも明確に、人々の内面が変わったことを描いてるようにも思えます。その点についてはどう評価していますか?
「確かにそうかもしれませんが、私自身は映画と私の本で、緒方さんの性格がそれほど違うとは思っていません。私は、彼のような人間に深い共感を持っています。自分の立場ででき得る限りのことをしたごく普通の人々です。彼らは決して自分が生きる当時の環境に対して先見の明があるわけではない。でも、私たちの大半がそうだと思います」
「私たちは与えられた仕事に最善を尽くしますが、しばしばあらがえない大きな力にのみ込まれてしまいます。作家でもジャーナリストでも、法律家でも教師でも、私たちがしたことが社会のより大きな構図の中で、どのように寄与するのかはよく分かりません。ですから、私は緒方さんのような登場人物に大きな共感を覚えるのです」
「映画において緒方さんはオムレツの話を熱心にしていました。それは小説でも同じです。彼らはオムレツの作り方について語り合っていました。このことは、より大きな変化を象徴するものです。つまり彼は、異なる世界と異なる価値観を受け入れるために変わったのです」
「悲しいことに、ある年齢に達した人は、たとえ表面的に変わったとしても、根源的に変わることはできません。人はその人なりの存在にしかなれないのです。人が別の人間に変わるには、あらゆる意味において人生は短すぎる。これは人間個人にとっての悲しい現実です。一生のうちに価値観が変わるような機会は一度あるかどうかではないか、と私は思うのです」
「ですが、社会や国は何度でも生まれ変わることが可能です。この映画では、1952年の日本、そして世界が価値観を変革させることに成功し、非常に前向きにダイナミックに変わっています。価値観の変革は個人にとっては手遅れでも、国家や社会にとっては遅すぎるということはない。チャンスはまだまだあるのです」
(3)多大な努力で維持された奇跡の平和
―戦後80年たちましたが、今も核の脅威、戦争の脅威は深刻です。その意味でも今年、この作品が映画化されたことの意味は大きいと思います。
「戦後80年の年に重要なことは、過去の痛みを思い出すだけではなく、80年の平和を祝福することではないでしょうか。というのも、歴史的に見た時に、こうした平和な時期があるのは非常にまれだからです」
「もちろん悲劇的な衝突はいくつも起こりましたが、日本やヨーロッパ、アメリカは平和と繁栄を享受してきたのです。こうした平和は現代に生きるわれわれには簡単で普通のことに思えますが、20世紀の前半を振り返れば、決して普通の状態ではありませんでした。現在の平和は、20世紀前半の恐ろしい教訓の上に、多大な努力を払って維持されてきたのです」
「今日において私たちは平和に満足して、それがいかにもろいものかを忘れてしまっている。そのことこそが真の危機なのです」
「今、この瞬間も危険が進行しています。第2次世界大戦後に国連など多くの国際機関が設立されました。国際通貨基金(IMF)や世界銀行といった経済機関、外交条約や通商条約も、戦争が絶えない恐ろしい50年余の影の中で作られたのです。そうした国際機関や条約がまさに今、挑戦を受けています。人々は国際機関を解体して倒すとさえ語っています」
「こうした国際機関や条約にこそ、私たちの平和が懸かっていると私は考えています。個人が平和を願っても十分ではないのです。外交的にも強力な機関を作り上げることで、奇跡と言ってもいいような80年の平和を達成することができたのです。だからこそ、今は非常に危険な状況なのです」
「核戦争の危険性も再び高まっています。かつて核戦争は冷戦と強く結びついた問題でした。冷戦終結とともに私たちは、核兵器が目の前から消え去ったように感じていました」
「ですが今日、多くの国が核兵器を保有し、AIを用いた兵器が、単に武器としてではなく、戦略を決定するツールとして進化した結果、私たちは核紛争の可能性という非常に危険な状況に再び至っているのです」
(4)戦争の記憶を“売る”道を
―日本は唯一の被爆国で、今も被爆者はいますが、やがて記憶は薄れていく。どうその記憶を伝えていけばいいのか。日本は核廃絶に向けて何をしていけばいいでしょうか?
「これが、私たちが危機的な状況にいるというもう一つの理由ではないでしょうか。第2次世界大戦、そして核による攻撃を体験した私の母を含む多くの人々はすでに亡くなっています。私たちがどのようにその記憶を保ち続けるのかというのは、非常に難しい問いです」
「私は何年も前に1週間ほど、アウシュビッツを訪れました。そこではホロコーストを生き延びた人たちが亡くなる中で、どのように記憶を保存するかということを巡って多くの議論が交わされていました」
「敬意を欠いた物言いかもしれませんが、私は、記憶を少しでも“パッケージ化”すべきだという考えに賛成です。マーケティングというと、ひどい発想に聞こえるかもしれませんが、10代の若者や学生たちが自分たちに関連のあることだと思える形にしなければ、記憶というものは死に絶えてしまうのではないかという危機感があります。そうしなければ、私たちとは直接関係のない神話、『ロード・オブ・ザ・リング』のようになってしまう」
「ですから、私たちが想像力を使って、この記憶をなんとか若い世代が理解し、自分たちが今生きている世界や未来に深く関係があるのだと感じられるように新しくデザインをして、パッケージ化してみせなければいけないのです。葬式のように、ただ過去にあった痛みや脅威を思い出すだけでは不十分なのです」
「ひょっとしたら、こけおどしの仕掛けのように感じるかもしれませんが、私たちは若い世代に過去の記憶を“売る”という道へと進まなければならないと考えています」
「私たちの世代は戦争を経験してはいませんが、戦争を経験した両親に育てられ、会話を交わしてきたという意味で、新しい責任を背負っているのかもしれません。私たちは戦争によって大きな影響を受けてきました。ですから私たちは、若かった頃には考えてもみなかったような形で、新しい責任というものを背負っているのです」
「若い頃は、戦争の話なんて聞きたくもありませんでした。私の両親の世代はイギリスでも、ヨーロッパでも、そして日本でも、戦争のことを語ってきました。一方で私たち若い世代は関心を払っていませんでした。しかし今、私たちは戦争体験に最も近い立場にあり、記憶を後世に伝えるという意味で義務を負っているのです」
「若い世代、特に子どもたちに、戦争の記憶が彼ら自身の安全と幸せと繁栄に強く結びついていると感じられるようにすることが重要になってくるのです」
 ポストする
ポストする