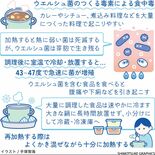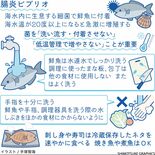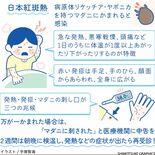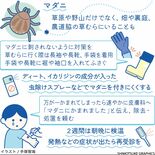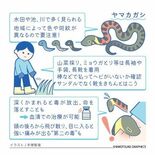黄色ブドウ球菌は伝染性膿痂疹(とびひ)を起こす菌ですが、浅い傷の化膿(かのう)だけでなく、食中毒を起こすこともあります。黄色ブドウ球菌には多くの種がありますが、その中に菌が増えるときに毒素を産生する菌がいて、その毒素が、食べ物と一緒にヒトの口に入ると毒素型の食中毒を起こすのです。
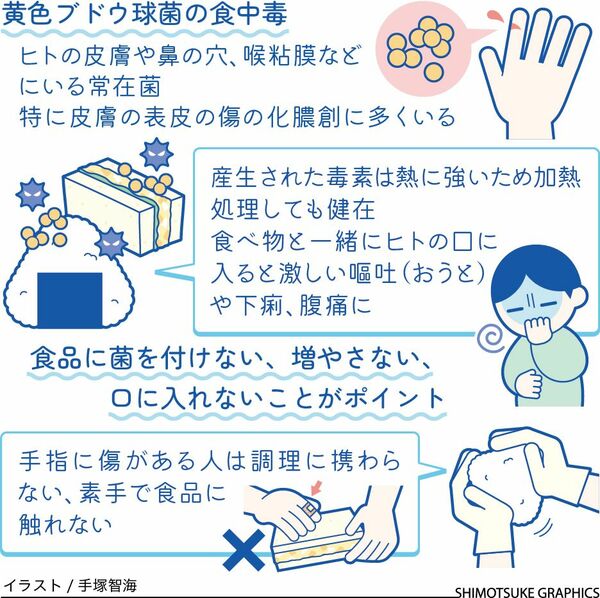
残り:約 768文字/全文:925文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする