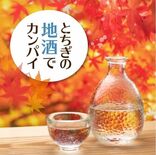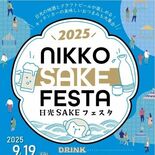「ワインの輸出額はフランス産だけでも1~2兆円。日本酒の輸出が増えているといっても400億円超。日本酒が伸びる余地はまだまだある」
そんな日本酒の立ち位置から講演を始めたのは、新潟大日本酒学センターの平田大(ひらた・だい)副センター長だ。講演は栃木県酒造組合杜氏研修会(会長・上吉原正人(かみよしはら・まさと)北関酒造杜氏)が主催し、7月に「日本酒学(Sakeology=サケオロジー)」をテーマに開かれた。県内酒蔵の杜氏や県産業技術センター食品技術部研究員らが参加した。
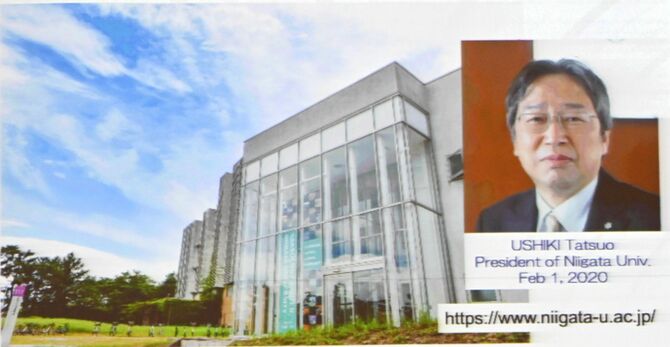
そもそも「日本酒学」とは。記者は醸造学や発酵学といった学問はよく耳にしていたが、恥ずかしながら日本酒学の存在すら知らなかった。しかし平田氏の講演を聴いて、日本酒の魅力をますます深く知ることができ、その取り組みに感動すら覚えた。
日本酒学とは新潟大が提唱し、2018年4月に同大で創設された世界初の学問だ。新潟県は酒蔵数が89社と全国最多で、全国3位の日本酒課税出荷数量を誇る。その量は以前に比べ減ってはいるものの、国内シェアが8・3%に伸び、吟醸酒では約21%に上る。輸出も新型コロナウイルス禍以前に戻りつつあるという。全国唯一の県単独の醸造試験場を持ち、日本酒イベント「にいがた酒の陣」は大人気で、順風満帆に見える。それでも平田氏は「でもわれわれの中には、何か『ピース(組を成すものの一つ)』が足りないという思いがずっとあった」と明かす。

それはワインならワイン学があるように、新潟県が誇る日本酒をアカデミックな側面から支える、製造法に限らない社会、文化、健康との関わりまでも領域とした「日本酒学」ではないかという思いだった。
2016年9月、経済科学部と農学部の教員が新潟県酒造組合に出向き、会長に提案したことがきっかけになった。翌年5月には新潟大、新潟県、同組合の3者が日本酒の文化的・科学的な幅広い分野を網羅する学問分野「日本酒学」の構築について、国際的な拠点の形成とその発展を目指して連携協定を締結した。
18年4月に「新潟大日本酒学センター」を開設し、経済科学部、農学部、医学部など10学部共通文理融合型の教養講座として開講した。当初、受講者数が集まらないときは新潟県内の酒類関係者にも参加を呼び掛けることも考えていたという。ところがふたを開けると受講者が殺到した。定員200人に対し、800人超が応募し、急きょ定員を300人に増やしたが、抽選に漏れた学生からは苦情が相次いだ。講義は大きな講堂で行われたが、立ち見が出る始末。その後も受講希望者が絶えないという人気講座になっているという。


日本酒学の取り扱う領域は、原料(水・酒造好適米等)、微生物による醸造・発酵の知識と技術、そして日本酒が消費者の手に届くまでの流通や販売、マーケティング、さらには醸造に関連する気候や風土、地理的表示(GI)などの地域性、歴史や酒税、醸造機器、日本酒のたしなみ方や健康との関わりなど多岐にわたる。
カリキュラムは3コース。基礎コース初回は学長、組合会長による講義が行われ、製造法以外にも日本酒のマナー、アルコールと脳、日本酒と料亭・花街の文化、日本酒と食・フードペアリングなど幅広く、実習や演習もあるなど、私でも受講したくなるような内容だ。市民講座も開かれ、地域挙げての日本酒学の盛り上がりを感じる。22年には大学院博士課程も開講し、社会人も学んでいるという。センター内では試験醸造できるほか、新潟県醸造試験場とタイアップした日本酒の商品化も行っている。
新潟大は日本酒学創設当初から「世界」を見据えていた。19年にはワイン本場フランスのボルドー大、20年には米国のカリフォルニア大デービス校とそれぞれ交流協定を締結した。現在は学生を定期的に留学させている。国内でもワイン科学研究センターのある山梨大、焼酎・発酵学教育研究センターのある鹿児島大と連携協定を結んでいる。

若者のお酒離れ、特に日本酒離れが指摘される中、新潟大のこの盛り上がりはどうしてなのか?。聴講した杜氏が質問した。
平田氏は「米処、酒処の新潟にせっかく来たのだから、日本酒を学びたい。20歳未満の学生はお酒のマナーを学んできちんと飲める大人になりたいというのが学生の声でした」と回答した。ただ「私たちが気付いていない、何か学生(の心)に刺さるものがあるんじゃないかと思っている」とも加え、現在、大学院生が取り組んでいる「Z世代の日本酒に対する志向性」の研究成果に期待を寄せた。
また平田氏自身は日本酒酵母とがん克服の研究のほか、「(お酒に)人は心で酔うものだと思っている」とも述べ、物質的ではない、心に由来する日本酒のおいしさに関する研究を進めていることも紹介した。
日本酒学は神戸大、広島大、山形大といった日本酒造りが盛んな県でも開設され、広がりを見せる。栃木県も地酒のおいしさなら決して引けを取らないと思っていただけに、新潟県酒造界における産学官の結び付きの強さ、新潟大の先進性に圧倒される思いがした。うらやましい限りだ。
栃木県内の大学でも独自立ち上げが難しいなら、新潟大と連携した講座を設けるなど、日本酒学を切り口に若い人に日本酒の魅力を伝え、ファンを増やす仕掛けをつくることも一考に値するのではないか。そんな思いを深めた。(伊藤一之)

 ポストする
ポストする