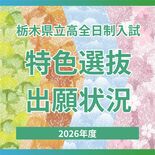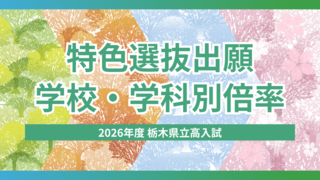「バンカーがなければ」という話をしたが、今回はカップについて触れてみたい。
「カップがもう少し大きければ」と願うプレーヤーも多くいるのではないか。タカ坊もパターイップスに悩まされて十数年。下りの短いパットは手が動かないことがしばしばだ。傾斜のきつい下りパットでは2度打ちも珍しいことではない。「(直径が)あと5センチ広ければ、イップスは治る」と、一回り大きなカップを切望する日々だ。
残り:約 896文字/全文:1098文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする