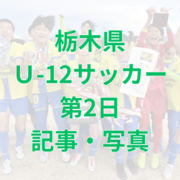地域に住む外国人に、日本語や日本の習慣を学ぶ機会を提供する「日本語教室」は、多文化共生社会の基盤の一つとして重要な役割を持つ。しかし県内9市町では、いまだ教室が一つもない「空白地域」となっている。
県の統計によると、県内在住の外国人は2022年以降、増加し続けており、アジア圏を中心に今年10月末時点で5万5千人を超えた。全市町で増えており、日本語を学びたい外国人の増加も見込まれる。行政や企業、民間ボランティアらが連携し、空白地域の解消を急ぐ必要がある。
地域の日本語教室は、市町の国際交流協会や民間団体によって運営されている。主に留学生を受け入れる「日本語学校」とは異なり、無料または実費程度で、地域の外国人に広く開かれている。
日本語学習の支援者の多くはボランティアで、60代~70代が多く活躍している。外国人にとっては日常生活に必要な言葉だけでなく、日本の習慣や文化に対する理解を深め、地域社会との接点を持つきっかけにもなる。
県によると、県内には4月1日現在で16市町に計53教室ある。しかし矢板、上三川、益子、茂木、市貝、芳賀、塩谷、那須、那珂川の9市町には教室がない。県などによる聞き取り調査では「要望はあるが職員の不足で対応できない」「教室に関する問い合わせを聞いたことがない」などの理由が挙げられたという。外国人施策の担当部門そのものがない自治体もあり、ニーズの把握もままならない実態が浮かび上がる。
一方、教室がある自治体でも、外国人が多い地域では定員いっぱいで新たな希望者が入れないケースもある。県国際交流協会などがオンラインによる学習支援を行っているが、地域社会との交流という点を考えれば、身近に通える教室があることが望ましい。
空白地域の解消とともに、希望者の増加に対応するには、支援者となる人材の確保が必要だ。県や市町は研修の開催などを幅広く周知し、掘り起こしに努めるべきだ。
育成就労制度への移行を見据え、外国人労働者を受け入れる企業との連携も強化しなければならない。県は本年度、日本語教室のない市町の企業への聞き取り調査を行うという。ニーズを把握し、市町とともに日本語教室の設置に向けて取り組んでほしい。
 ポストする
ポストする