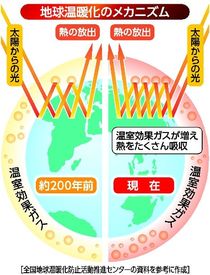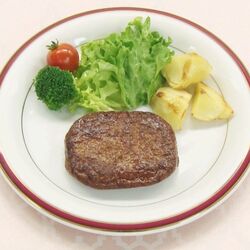50年以上前の少年時代、「南に行って一度は捕まえてみたい」と憧れたチョウがいま、宇都宮市内で当たり前のように飛んでいる。
「夢にも思わなかった」。とちぎ昆虫愛好会の高橋滋(たかはししげる)会長(69)は戸惑いを隠せない。
ナガサキアゲハ、ムラサキツバメ、アカボシゴマダラ-。2000年代以降、南方系の種が県内で相次いで発見されている。
チョウの生態に詳しい山梨県富士山科学研究所の北原正彦(きたはらまさひこ)専門員は「特にナガサキアゲハの分布域の北方拡大は、温暖化が主因と言える」と解説する。
北原さんは1940年代以降のナガサキアゲハの採集、目撃記録と、付近の都市の気温を解析。年平均気温が約15度、最も寒い月の平均気温が約4度を超えるにつれ、西から分布域が広がるなど、温暖化と相関関係があると結論付けた。
研究では、2010年時点での生息北限を本県南部と推定した。高橋さんによると、現在は既に県央部で冬を越えているという。
◇ ◇
「今まさに栃木県が北限」。昨年10月、県立博物館自然課の林光武(はやしてるたけ)課長が水槽の中のヌマガエルを指さし説明した。南方系のカエルだが、数日前、栃木市の田んぼで捕まえたという。「県南なら、もう誰でも簡単に見つけられる」
1999年9月、佐野市の渡良瀬川で初めて見つかったのを機に、周辺の市町を調べた。生息域は段階的に拡大、2年前には鹿沼市、昨年は壬生町で発見された。北上のスピードは、ほぼ年1キロのペースだ。
ヌマガエルは暑さにはめっぽう強いが、気温1度だと2週間程度で死に、氷点下1度だとほとんど生きられない。「温暖化により冬の寒さが和らぎ、越冬できるようになったことが要因だろう」と考察する。
◇ ◇
分布域を北へと広げているのは動物だけではない。
「かなり暖地性の植物が増えてきている」。日光市内の植物の分布調査や保護などに取り組む「今市の自然を知る会」の駒倉政夫(こまくらまさお)会長(71)は話す。
会は日光杉並木街道に自生する植物について、1980年代後半と2000年代後半に調査。街道を12区間に分けて、植物の種類などを調べた。
結果を比べると、2回目の調査では主に関東以西の暖かい地域に分布する植物を多く確認した。常緑低木のマンリョウは全区域で初めて見つかった。「30年前、暖地性植物は宇都宮や鹿沼市寄りの一部でしか見られなかったので驚きだった」と駒倉さんは振り返る。
県植物研究会幹事の長谷川順一(はせがわじゅんいち)さん(81)は「特にシダやラン類は、胞子や種子が微小で風に乗って飛散しやすい。温暖化に伴う分布の拡大が分かりやすい」と説明する。
温暖化が進めば、森林を構成する植物の種類が変わり、景観も変化していく可能性がある。いまは、その過渡期なのかもしれない。

 ポストする
ポストする