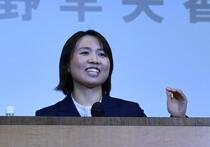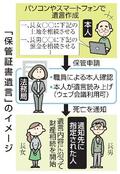自社業務の効率化を考える際に、当たり前のようにDX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が使われる世の中になってきました。業務効率化を図るために何から手を打つべきか、自社に合ったDX推進とは何か? 多くの経営者がDXに対するさまざまな疑問を抱えながら、未来に向けた経営改革の道を模索しています。そんな中、「DXが中小企業を変える!DX推進セミナー」(主催:下野新聞社、共催:NTT東日本栃木支店、あしぎん総合研究所、TMC経営支援センター)が12月5日(月)、ベルヴィ宇都宮で開催されました。※本セミナーは会場での聴講のほか、聴講希望者へのWeb配信も行われました。 企画・制作 下野新聞社営業局
ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪 貴子 氏

大切なのは、トップが先陣を切りDX推進への熱意を伝えること
ダイヤ精機株式会社は1964年に、私の父が東京大田区に創業した町工場です。2004年に父親が急に亡くなり、専業主婦だった私が社長に就任して19年が経ちました。
DX、最初の一歩
社長になって、最初に行ったのはリストラです。実は父が急逝する何年も前に、父から「経営を手伝ってほしい」と2度頼まれて入社し、私自身が2度リストラされています。社員のリストラは非常に厳しい選択でした。しかし、私には時間がなかったんです。今でこそ女性活躍と言われていますが、当時は「町工場の二代目を娘が継いだ。経営のケの字も知らないらしいぞ、潰れるぞ、近づかない方がいいぞ」、そんな噂が流れ、合併を持ちかけてきた銀行の支店長に「私の経営をまだ見ていないじゃないですか、私は半年で結果を出す。結果が出なかったら好きなようにしていい」と言ってしまったんですね。
結果、リストラをして、残った社員に自分の経営をぶつけるために「3年間の改革」を断行しました。1年目は基盤強化を行いました。「おはようございます」の声掛けから始めて整理整頓を徹底し、1カ月後に4トントラック1杯分のものを廃棄しました。通路が広くなり、物を探す時間がなくなり、作業の効率化が図れました。1年掛けて製造業の基本の教育を行いました。
2年目は、過去40年間の業績と強みを分析して、生産管理システムの全面変更、DXを行いました。仕事を出してくれる企業に出向いて「なぜ仕事を出してくれるんですか」って聞きました。答えは「対応力」でした。「電話したらすぐ来てくれるでしょ。納期対応してくれるでしょ。特急対応してくれるでしょ。だから出しているんだよ」って。そこが評価されているのなら、対応力を強化しなければならない。でも実際にはお客様からの問い合わせに職人さんが頭の中だけで対応していたんですね。これでは続かないということで生産管理システムの全面変更に踏み切りました。
そして3年目。受注入力をしてからの生産情報の一元管理ができる進捗管理システムを導入しました。自社が考える生産管理システムが実現可能なメーカーを探して社内プレゼンも行い、職人の意見を入れてシステムをカスタマイズしました。旧システムからの切り替えは3カ月で成功しました。このとき私は、リーダーの役割というものは、まず課題に対する目的と方向性をしっかりと社員に示すこと。そして自分のモチベーションを上げて社員を巻き込むことだと実感しました。
DXはなかなか費用対効果が見えにくいのですが、1年経つと営業利益、経常利益に明らかに差が出てきました。これからDX化を考えているという方は、ぜひやってみてください。そして1年後の結果を見てください。必ず違いが分かると思います。
2回目のDX
最初のDXから15年後、人材確保に取り組んだ結果、弊社は技術を維持したまま社員の年齢構造は若手が中心のピラミッド構造の形成に成功しました。しかし、生産性は落ちてしまいました。この課題解決のために2回目のDXを行い、双方向の情報共有システムを導入し、見積りや受注システム、生産システムも刷新し、社内ネットワークを再構築しました。そこで分かったのは、一つの部門だけではなく、トップが先陣を切ってDXを推進するという熱意を全社員に伝え、業務の棚卸しをして無駄を洗い出し、全員一致で取り組むことの重要性です。私は初めからすべての機能を使おうと思わず、社員にはとにかく3週間使ってもらって習慣化を図ることで、二度目のDXに成功しました。チャレンジ精神を持ってイノベーションを起こすことが大切です。
東日本電信電話(株) 栃木支店 支店長 小林 博文氏

デジタル化の流れが止まらないということは、皆さまも常々感じていると思います。今やネットとスマホがなければビジネスが成り立たない時代となりました。AI技術も進化し、過去はプログラミングによって指示を出して作業を進めていましたが、今はディープラーニングによってAI機器が自分で考えて進めていくという時代です。
この流れを受けて、ビジネスモデルは機能性や品質を訴求する「モノ」売りから、顧客体験や感動を提供する「コト」売りへと変化しています。デジタルは、社員の働き方の評価も変化させます。デジタル技術の導入により効率化を図り、これまでも短い時間で仕事ができるようになった結果、新たに生まれた時間でどのような企業価値を創出するかというのがこれからの課題です。ここを目指していかないと企業としての存続が難しくなります。競争が激しい時代だからこそ、より付加価値の高い業務にリソースをシフトしていくことが必要です。
DXの究極の目的は顧客基点の付加価値創出や新たなビジネスモデル創出による収益拡大ですが、デジタイゼーション、デジタライゼーションによる効率化・コスト削減という点もDXの効果として見逃すことはできません。
それぞれの企業が抱える課題に応じて、DXにはさまざまな種類とアプローチ法がありますが、最後は経営者の選択になります。社内の多岐にわたる経営課題の解決に向けて、投資効果等の経済合理性やリスクを踏まえて決断していくことが大切です。世の中に無数に存在しているデジタルツールをそのまま導入できれば低コストなデジタイゼーションが実現可能ですが、自社の状況に合わせたカスタマイズやプロセスの見直しが伴う場合は時間とコストがかかります。デジタル人材の育成や外部パートナーの協力も必要です。
最も大切なのは、スモールスタートで小さな実績を積み上げ、経営サイドと現場が成果を共有・共感することから次のステップに繋げていくことです。リスクの大きなDXを試みて失敗したという事例はたくさんあります。デジタル技術の活用を定着させていくためには、働き方・社内文化・社員のマインド改革に根気よく取り組んでいくことも必要になってくるのではないかと思っています。
TMC経営支援センター 代表取締役社長 葛西 美奈子氏

働き方改革関連法が順次施行され、企業にはさまざまな改善が求められています。労働人口減少に伴う人材不足、若手人材の低い定着率、過労死や過労自殺などの社会問題、労働生産性の低さ等の改善に向けて働き方改革が重要となっています。職場の改善をしない組織は人材確保やコスト削減で後れを取り、競争力が低下していきます。
さらにコロナ禍により雇用環境も大きく変化しています。コミュニケーションが希薄化し、人材の成長や働く意欲が低下し、メンタル不調を訴えて休職する若者も増加しています。この状況下で企業の収益性を維持するためには、働き方改革と合わせて生産性向上に取り組むことが不可欠となります。
人材活用の促進、業務手順の見直し、設備投資、ICT(情報通信技術)の活用、デジタル化とRPA(ロボットによる業務の自動化)導入、業務管理と目標管理の強化等が考えられますが、この中でも特に、設備投資・デジタル化による生産性向上には高い即効性が期待できます。設備投資では、手作業を機械化したり従来よりも性能の高い機器を導入することで生産性を向上させることができます。デジタル化では、ICTを活用した労務管理や夜間業務のデジタル化、RPA導入により、社員の負荷軽減や時間外労働削減、納期短縮、ヒューマンエラーの低減などが実現し、コスト削減や人材不足対策、受注拡大、顧客サービス強化、新たな業務への挑戦などの効果を得ることが可能です。
DX推進は競争力を高めるための重要課題のひとつと認識し、ぜひ多くの企業に取り組んでいただきたいと思います。
NTT東日本 栃木支店
《問い合わせ》
0800-800-0544 営業時間/9:00~17:00(土・日・休日・年末年始を除く)

 ポストする
ポストする