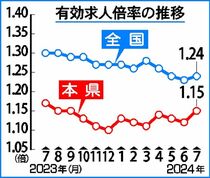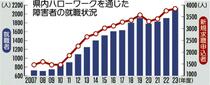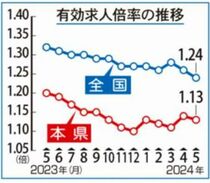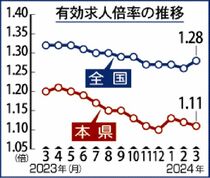2022年6月1日時点で、県内企業(従業員31人以上)の70歳以上の労働者数は8847人で、統計を取り始めた13年から10年間で約6倍に増えたことが8日までに、栃木労働局の調査で分かった。21人以上の企業では、1万79人に上る。70歳以上の人が働ける制度がある企業も増加傾向で、全体の4割を超えた。少子高齢化などを背景として、高年齢者の就業意欲の高まりと、即戦力として人材を確保したい企業側の意向の合致があるとみられる。
同労働局によると、調査は従業員21人以上の県内企業3291社からの報告をまとめた。20年までは31人以上の企業を対象とし、21年から拡大した。

21年4月施行の改正高年齢者雇用安定法で、70歳までの就業機会の確保は企業の努力義務になった。そうした中、22年6月1日時点で70歳までの就業確保措置を実施する県内企業は1013社。前年同期比2・4ポイント増の30・8%で、全国平均の27・9%を上回った。70歳以上まで働ける制度のある企業は1344社で同2・2ポイント増の40・8%。全国平均は39・1%だった。
従来統計の対象だった31人以上の企業でみると、13年の70歳以上の労働者は1515人で全体の0・6%。22年は8847人で、2・9%に増えた。企業は継続雇用や定年制の廃止などで対応している。
電気・電子機器製造の中村機器(小山市)は19年、グループ9社で65歳定年制を導入した。定年後も雇用を継続し、70歳以降も本人の体調や希望に応じて働ける環境を整えた。全従業員68人のうち11人が65歳以上で、70歳以上は6人いる。
勤続34年の柴山綾子(しばやまあやこ)さん(68)は「重労働は上司が手伝ってくれるなど、気配りで安心して働ける」。60歳で入社した女性(72)も「健康なら75歳まで続けたい」と意気込む。同社にとって熟練労働者は大きな戦力となっている。
国は高年齢者を積極採用する企業の求人情報などを提供する「生涯現役支援窓口」を設け、県内では6ハローワークに設置。22年度は宇都宮、小山、大田原に専門アドバイザーが常駐し、個別プラン作成などを支援する。同労働局は「いかに企業と高齢者を結びつけるかが重要。アドバイザーも生かして今後の雇用につなげたい」としている。

 ポストする
ポストする