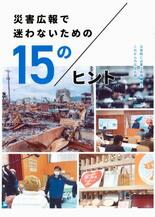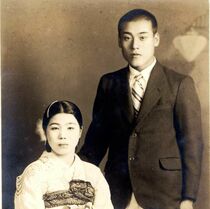父は食油や穀物を扱う卸問屋でした。統制配給で自由に商売はできなかったようです。それでも空襲で家が焼けるまで、生活に困ることはありませんでした。
〈12歳だった1945年7月、宇都宮空襲に遭い、宇都宮市南大通りの線路の西沿いにあった家から避難した〉
路地に六角形の筒状の物が束になって落ちていて、ちろちろと青い火が出ていました。焼夷(しょうい)弾です。それをまたいで逃げました。近所の同学年の子がやけどをして「痛いよ、痛いよ」という声が聞こえました。
家族で(線路東側の)簗瀬のキュウリ畑に身を潜め、爆撃が収まるのを待ちました。すると父は、ひょうきんな感じで「ほら、これでも食べろ」と、目の前のキュウリをもぎ取って私と姉に差し出したんです。それをかじると、「もう大丈夫」と思えました。張り詰めていた心をほぐしてくれたのね。
家は焼失してしまったけれど、大谷石の蔵は残りました。逃げる前、父がバケツからみそをつかみ、勢いよく扉の隙間に投げつけて、火が中に回らないようにふさいだのです。しばらくの間、蔵で暮らしました。
〈終戦後、食糧不足は一層深刻化し、数年間、統制が続いた〉
急に貧しくなって戸惑いました。ある日、使いに行った魚屋さんで切り身を三つ買ったら、握りしめていたお金を全部取られてしまいました。家に帰ると、母に「返してきなさい」と言われ、店に戻りました。切ない思い出です。
父は近所の人を雇って納豆の工場を始めました。生活を立て直すまで何年もかかりました。
戦災で家が焼けた人と焼けなかった人の差は本当に大きいの。今は災害などで被災すると見舞金などが支給されるけれど、当時は何もありませんでしたから。戦争は理不尽です。

 ポストする
ポストする