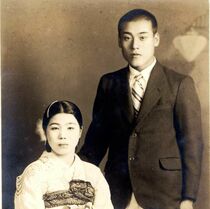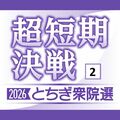ウクライナで起きた戦争の映像を見ると、宇都宮空襲の体験がよみがえり、つらくなってテレビを消してしまいます。
〈1945年4月、12歳で宇都宮第一高等女学校(現・宇都宮女子高)に入学。同年7月12日夜、空襲で現在の宇都宮市中央1丁目にあった家が被災した〉
「ドン」という音で目が覚めました。窓から外を見ると、周囲は真っ赤な炎でまぶしく、近くの松が峰教会が燃えていました。防空頭巾だけをかぶり急いで家を出ながら、本箱に大事にしまってあった刺しゅう糸のことが頭をよぎり、玄関の本棚にあった「芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)全集」や「銭形平次捕物帖(ぜにがたへいじとりものちょう)全集」が惜しい、とも思いました。
夜が明けて家に戻ると、骨組みまで焼け落ちていましたが、母が前夜、準備しておいた大豆入りのご飯が大谷石のかまどの上で炊けていたんです。皆で変に感激し、焦げた梅干しをおかずにご飯を食べました。そのおいしかったこと!
〈空襲の約2週間後、宇都宮駅近くで、機銃掃射に狙われた〉
戦闘機が、操縦士のサングラスと白いマフラーが見えるほど低空飛行で近づいてきたんです。地面に伏せると、体の脇を「タタタタタ」と弾丸が走り、乾いた土煙が立ちました。その後50代になっても、その時の恐怖で夜中に目覚めることがありました。
〈8月15日に終戦。夜の灯火管制が解除された〉
「電灯を付けて本が読めるんだ」と思いました。くだらないことだけど、すごくうれしかったです。
でもその頃はまだ、地下に掘った防空壕(ごう)の焼け跡で、電気のない生活をしていました。そんな生活を見られるのは恥ずかしかったけれど、友達は何も言わず、毎朝一緒に笑顔で登校してくれました。優しい友達で、ありがたかったですね。

 ポストする
ポストする