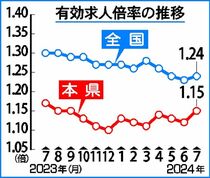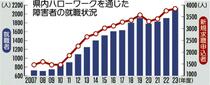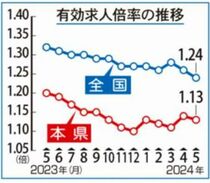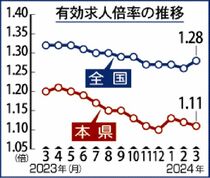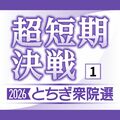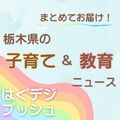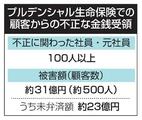同社が全国の学生を対象に毎年行う「Uターン・地元就職に関する調査」では、地元と認識する都道府県を選ぶ設問(複数選択可)があり、卒業高校の所在地を選ぶ回答の割合が各地の学生とも90%を超える。
一方で「所在地以外の県も地元」とした回答が20%を上回る場合、同社は「地元の認識範囲を捉える上で統計学的に有意」とみており、田沢准教授は「地元と認識すると就職に抵抗感が小さい」としてデータを活用した。
2015~18年卒生が対象の過去4回の調査で、本県出身者が「所在地以外の県も地元」とした回答が20%を上回ったことがあるのは茨城と群馬、埼玉、東京の4都県。関東では最多で「地元と考える範囲が相対的に広い」(田沢准教授)結果となった。田沢准教授は「栃木は交通網が発達しているため、通勤できる(地元の)範囲が広いと考えられる」と分析する。
対照的に、他県出身者で「栃木を地元」とする回答が20%を上回ることはなく、田沢准教授は「悲観的に捉えれば、栃木の学生の目は他県にも向き、他県の学生の目は栃木に向いてない」と指摘した。本県・他県出身の学生の関心を引くためには、県内事業所のインターンシップを充実させることなどを提案した。
同調査では「地元就職希望率」(最も就職したい県と卒業高校所在地が一致する割合)が下落傾向にあり、18年卒生は全国平均で51・8%だった。関東各県の学生は全国を下回る傾向にあり、本県出身者はここ数年、30%台で推移している。

 ポストする
ポストする