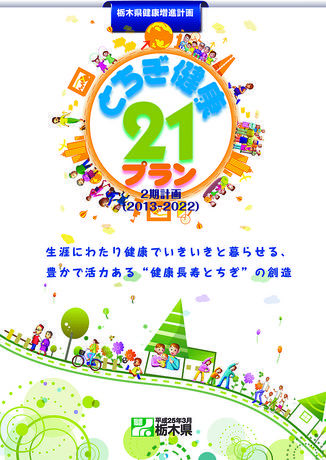
たばこの煙には、依存症の原因となるニコチンをはじめ、タール、一酸化炭素、ヒ素、カドミウムなど200種類以上の有害物質が含まれ、そのうち発がん性が分かっているものだけでも約60種類あります。有害物質は、煙に触れる呼吸器だけでなく、血液中に溶け込んで全身に行き渡ります。このため、長期間にわたる喫煙により、がんや心臓病、脳卒中、歯周疾患、胃かいよう、十二指腸かいようなどが発症しやすくなります。
例えば、非喫煙者を1・0とした場合の喫煙者のがんによる死亡リスクは、肺がんでは男性4・5倍、女性2・3倍、肝臓がんでは男性3・1倍、女性2・2倍、咽頭がんでは男性32・5倍、女性3・3倍です。ほかの疾病による死亡リスクも、虚血性心疾患では男性1・7倍、女性1・9倍、くも膜下出血では男性1・8倍、女性1・7倍と高まります。
また、未成年者の喫煙は、成長に悪影響を与えるほか、身体に酸素が十分に行き渡らず、持久力低下をもたらします。喫煙を始めた年齢が若いほど、ニコチン依存症になりやすく、がんや心臓病発症のリスクも高まるとされています。
ただ、こうした喫煙が健康に与える影響の認知度については十分と言えないのが現状です。平成21年度県民健康・栄養調査によると、「肺がん」「妊娠への影響」については男女とも高い認知度を示していますが、一方で「心臓病」や「脳卒中」については5割程度、「胃かいよう」や「乳幼児の突然死」「歯周病(歯槽膿漏など)」については4割以下にとどまっています。
室内またはこれに準ずる環境で、他人のたばこの煙を吸わされるのが「受動喫煙」です。建築物の気密性が高くなった現代では受動喫煙がますます深刻な問題となっています。
たばこの煙は、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」と、火の付いたたばこの先から出る「副流煙」に大別されます。たばこのフィルターを通過していない副流煙は主流煙より有害物質を多く含んでおり、喫煙が周りの非喫煙者の健康にも悪影響を及ぼすことははっきりしています。
非喫煙者の場合、たばこの煙を短時間吸い込むだけでも目の痛み、くしゃみやせきが出たり、頭痛、血圧が上がるなどの症状が起こります。受動喫煙が長時間、持続的に続くことにより、呼吸器の疾患や肺がん、心臓病、脳卒中などによる死亡のリスクが高まります。
特に小さな子どもは、たばこの煙によって大人とは異なるさまざまな影響を受ける可能性があります。例えば、気管支喘息、呼吸器感染症、小児がん、中耳炎などの病気を引き起こしたり悪化させる原因となるほか、身体発育の低下、歯肉の着色、言語能力の低下、注意力散漫などにもつながります。
妊婦への影響も深刻です。流産、早産や新生児の低体重化、将来の肥満、糖尿病のリスクが高まります。また、乳幼児突然死症候群(SIDS)は、家庭内に喫煙者がいることと密接な関連があることが報告されています。
喫煙が主な原因となる慢性閉塞性肺疾患(COPD)への注目が近年高まっています。たばこの煙などの有害物質を長期間吸ったために肺に炎症が起きる病気で、肺の機能障害が進行すると軽い動作でも息切れを感じるようになり、悪化すれば日常生活にも支障をきたすようになります。
また肺の炎症が全身にも影響し、体重減少、筋力低下や心臓病、胃かいよう、骨粗しょう症などの症状も起きます。さらに、肺がんを合併する可能性が高いことも知られています。
COPDは治療をせずに放っておくと命に関わる病気です。国内での死亡者は年間約1万7千人にも上ります。COPDによる肺の機能障害は完全には元の状態に戻りませんが、適切な治療を受ければ病気の進行を遅らせることができます。
COPD発症のリスクを減らすためにも、一日も早く禁煙することをお勧めします。
「とちぎ健康21プラン(2期計画)」は、喫煙に関する「目指すべき姿」として「①喫煙の健康に及ぼす影響について理解し、禁煙を希望する人全員が禁煙を達成しています②未成年者や妊娠中の女性は喫煙していません③受動喫煙のない社会で生活しています」を掲げ、左の図表に示す「目標項目」を設定しています。

 ポストする
ポストする












