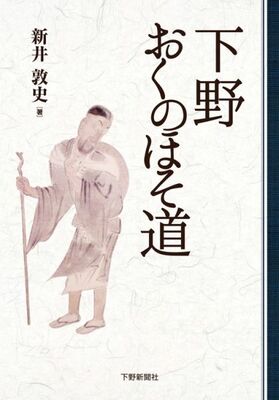下野おくのほそ道
新井敦史 著
定価 1,650円(本体1,500円+税10%)
四六判/並製/190頁
15/06
ISBN978-4-88286-589-6
下野新聞「県北・日光版」に1年間連載し、好評を博した特別寄稿「下野おくのほそ道」に、新たに多くの資料・写真を加え、新コラムも追加して待望の書籍化!
最高傑作「おくのほそ道」に結実する旅の資料を丹念にひもとき、特に22日間にわたって逗留した下野国内での様子を詳細に記述。県内に数多く残る「芭蕉句碑」も紹介し、名句の数々に迫る。
著者は大田原市黒羽芭蕉の館の学芸員である新井敦史氏。
【目 次】
第1章 芭蕉の生涯
名句との旅へ わが家で新春俳句没頭
誕生・武家奉公 俳諧相手役に召し抱え
江戸へ出る 新興の町に運命賭ける
江戸俳壇の名士 入門者集めた酒脱さ
三十七歳、人生の転機 「侘び」実践へ 深川退隠
仏頂和尚に参禅 漢詩的表現の可能性追求
旅の人生 草庵生活から覚悟の出立
「おくのほそ道」の旅 無常に生きる尊さを実感
不易流行 流転の中の永劫思う
上方漂泊 「猿蓑」書名由来の発句
「軽み」の俳諧 日常の風物に詩情探る
最後の旅へ 旅を住処に生きた証し
●コラム 芭蕉の里くろばね
第2章 「おくのほそ道」の旅 下野路
旅の初日 「旅立ちの時」惜別句
室の八島 和歌の伝統踏まえ詠む
鹿沼宿泊 芭蕉の宿泊先に諸説
日光東照宮拝観 推敲を重ね掲載句に
裏見の滝・含満ガ淵 出発点の自分をイメージ
那須野 少女との出会い清々しく
黒羽長期滞在 浄法寺邸の居心地良く
雲巌寺 仏頂和尚への尊敬の念
●補論 「おくのほそ道」雲巌寺の章に見える「若き人多く」の解釈について
修験光明寺 第二の出発点 黒羽を意識
那須の篠原 篠竹茂る原野へ足延ばす
玉藻の前の古墳・犬追物の跡 桃雪には及ばぬ「芭蕉」
八幡宮 殺戮の世、非業の死連想
歌仙興行 長期滞在支えた蕉門俳壇
黒羽出立 能動的な表現に斬新さ
高久家宿泊 高い声が、高い空から
那須湯本 旅の無事祈り京も思う
殺生石 荒涼とした風景捉える
遊行柳 「植て」に魅力ある説も
●コラム 国指定名勝「おくのほそ道の風景地」
●コラム 奥の細道サミット
第3章 「おくのほそ道」の旅 東北・北陸路
白河越え 奥州路で経験した最初の風流
福島県域を北上 笈と太刀、義経主従の面影
宮城県域を北上 「昔の姿失はず」に感激
松島 絶景に圧倒され発句を載せず
平泉 永遠なるもの 思い込め
立石寺 際立つ静粛さ見事に表現
最上川・出羽三山 急流実感、発句の推敲に
象潟 憂愁の景色をたたえる
越後路 雄大な眺望に漂う旅愁
越中路・金沢 「万葉集」を思慕する旅
曾良との別れ 悲しみに耐え旅の続行決意
那谷寺~汐越の松 奇石累々 美景厳かに
越前路 侘と風狂の色調
大垣 再び旅立つ惜別の情
●コラム 「おくのほそ道」諸本
第4章 栃木県内の芭蕉句碑を訪ねて
県南地区の芭蕉句碑① 見た事実十七音で示す
県南地区の芭蕉句碑② 名高い蕉風開眼の句
県南地区の芭蕉句碑③ 「古今和歌集」を踏まえて
県央地区の芭蕉句碑① 「軽み」を具現する発句
県央地区の芭蕉句碑② 想像すると思わず笑み
県北地区の芭蕉句碑 俳人の風格 山に準える
下野おくのほそ道
2015/6/17

 ポストする
ポストする